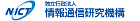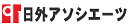「典拠」を含む例文一覧(56)
1 2 次へ>- 典拠となる故事
considered to be precedents, old rules and customs - EDR日英対訳辞書 - 典拠となる先例
a previous example that serves as a precedent - EDR日英対訳辞書 - その他典拠多数)。
There are many other authorities. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 引用されたすべての典拠をあげる
give credit to all authorities quoted - 研究社 英和コンピューター用語辞典 - 野守(万葉集の歌が典拠)
Nomori (Source: Verse in Manyo-shu, or Collection of Ten Thousand Leaves) - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 君は何か典拠があってそう言うのか
Have you any authority for your statement? - 斎藤和英大辞典 - どういう典拠があってそう言うのか
On what authority do you say so? - 斎藤和英大辞典 - 僕の言うことの典拠を明白にしよう
I will give you chapter and verse for my statement. - 斎藤和英大辞典 - 教育するときに典拠とするもの
the fundamental basis or authority on which education is grounded - EDR日英対訳辞書 - 過去の事柄で,現在の典拠や基準となるもの
past matters used as a precedent for the present - EDR日英対訳辞書 - 内容の典拠については年表を参照。
See the chronological table for the reference of authority contents. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 本朝世俗部の話には典拠の明らかでない説話も多く含まれる。
Additionally, many tales in the Honcho secular portion have no clear source. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 「四神=山川道澤」説の典拠となっているのは、『作庭記』である。
The "Sakuteiki Gardening Book" is source of the theory that equates the Four Gods to 'mountain, river, road and lake.' - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 特定の業務の典拠として使用され、相対的に不変であるコンピュータファイル
a computer file that is used as the authority in a given job and that is relatively permanent - 日本語WordNet - 嘉永年間(1848年-1854年)には本願寺広如の命により、「真宗法要典拠」を著している。
From 1848 to 1854, he wrote 'Shinshu Hoyo Tenko' under the order of Konyo, Hongwan-ji Temple. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 典拠は唐の南山大師道宣が著した『四分律行事鈔』。
Its source is "Shibunritsu Gyojisho" (one of commentaries of Vinaya Pitaka (ancient sutras in India)) written by Dosen (in pinyin, Daoxuan), a priest who lived in the era of the Tang Dynasty and was honorifically called Nanzan Daishi (Great Priest Nanshan). - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 「幽玄」「物真似」「花」といった芸の神髄を語る表現はここにその典拠がある。
Expressions such as "Yugen" (the subtle and profound), "Monomane" (impersonation) and "Hana" (flower), which indicate the essential points of performance, are based on this work. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - それぞれ独自の伊勢物語理解を展開し、それが能『井筒(能)』などの典拠となった。
They each developed their own interpretations of the text and provided sources for later works such as "Noh Izutsu." - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - このほか、『陸奥話記』を典拠とする話は、『扶桑略記』『十訓抄』などにもみえる。
Other works based on "Mutsuwa-ki" include "Fuso Ryakki" (A Brief History of Japan) and "Jikkinsho" (A Miscellany of Ten Maxims). - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 書かれている注釈の大部分は引歌や引詩の出典、史実の典拠を示したものである。
Most of the comments written in it give the sources of songs and poems and the bases of historical facts. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 奈良時代以降、日本の書は晋唐・宋・元・明清の書を典拠にしてきた。
Starting in the Nara period, calligraphy in Japan was based on calligraphic works in Jin-Tang, Yuan, or Ming-Qing. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - ※特に典拠の無い限り、『日本三代実録』『公卿補任』の記載による。
* Main references are "Nihon Sandai Jitsuroku" (Veritable Records of Three Reigns of Japan) or "Kugyobunin" (directory of court nobles); in case of other references, they are indicated respectively. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - ただし典拠となる漢籍には、このような考え方は存在しないとも述べている。
However, it is mentioned that such an idea does not to exist in the Chinese book as an authority. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 日本書紀の資料は記事内容の典拠となった史料と修辞の典拠となった漢籍類(三国志、漢書、後漢書、淮南子等)に分けられる。
The materials of Nihonshoki are classified into historical materials which became the authority of contents and Chinese classic books (Sangokushi (Three Kingdom Saga), Kanjo, Gokanjo, Huainanzi (The Masters/Philosophers of Huainan) and so on) which became the authority on rhetoric. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - (2)当事者は,聴聞日の少なくも1月前までに,書面の提出物及び典拠の束を登録官に提出し,同時にそれぞれの書面の提出物及び典拠の束を互いに交換する。
(2) The parties shall file with the Registrar their written submissions and bundles of authorities at least one month before the date of hearing, and shall at the same time exchange with one another their respective written submissions and bundles of authorities. - 特許庁 - その後編纂された延喜式の玄蕃寮格式も後世の統教権に基づく規制の典拠とされた。
Genba-ryo kakushiki (formality of the Bureau of Buddhism and Aliens) in Engishiki (an ancient book for codes and procedures on national rites and prayers), which was compiled later, was also considered as the basis of regulations grounded in tokyo-ken in succeeding generations. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - のちに本書を典拠として、建部綾足が『本朝水滸伝』を著すなど江戸時代中、後期の著述家に大きな影響を与えた。
The book greatly influenced many writers of the mid and late Edo Period such as Ayatari TAKEBE, who wrote "Honcho Suikoden" (Japanese Water Margin) based on the book. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 森鴎外らが訳詩集『於母影』(1889年)を出すにあたって、396番歌を題名の典拠としたことはよく知られる。
It is widely known that when Ogai MORI and others published the "Omokage" (Vestiges, 1889), an anthology of poems in translation, they used the 396th poem of the Manyoshu as the source for its title. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 1980年に『八犬伝の世界』を上梓した高田衛は、副題に「伝奇ロマンの復権」を掲げ、「典拠」に関する大胆な解釈を打ち出した。
In 1980 Mamoru TAKADA published "The World of Hakkenden" with a subtitle of 'Restoration of Fantasy Roman' and delivered an exciting interpretation of 'tenkyo' (accurate foundation). - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - このような、脇手のうちの2本を頭上に掲げる形の千手観音については経典に典拠がなく、その由来は未詳である。
There is no authority in the Buddhist scriptures about such a statue with a couple of its arm raising overhead, and therefore its origin is unknown. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - ※家督継承につき「諸侯年表」では慶長17年説を記すが、典拠とされている「藩翰譜」には所見がない。
*'Shoko Nenpyo' (The chronological table of feudal lords) stated and supported the theory that he inherited the family estate in 1612 but 'Hankanpu' (Genealogy of the Protectors of the Shogunate), which is considered to be an authority, does not mention about it. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - このほか典拠不明ながら、『古今著聞集』には甥と通じていたものの、後に男の通いが絶えて憂悶に苦しんだとする逸話を掲げている。
Other than this, "Kokon Chomon Ju" (A Collection of Tales Heard, Past and Present) tells that she had an affair with her nephew, and as he stopped visiting her, she experienced anguish. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 長崎でフィリップ・フランツ・フォン・シーボルトに師事したとされてきたが、最近では長崎遊学、シーボルト門下とする典拠はないとされる。
Sanei was believed to have studied under Philipp Franz von Siebold in Nagasaki, but it became clear that there is no such evidence. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 特に巻二から巻四までを充てた「践祚大嘗祭儀」は践祚・大嘗祭儀式の典拠として重要視されている。
In particular, 'Senso daijosai' stipulated in volume 2 to volume 4 is regarded as important as the authority of the rite of Senso daijosai. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 粘性率の数値及び測定温度等、参考としたデータと典拠を「根拠」に記載しておくこと。
3) Liquids and solids, not gases, are subject to classification, since the hazard relates to aspiration of liquids/solids rather than aspiration of suspended matter in the gas phase. - 経済産業省 - 権威ある典拠からいくつか抜き出してみると、この単純な言葉に以上のような意味が与えられているのです。
Such are a few of the significations attached to this simple word which may be culled from authoritative sources; - Thomas H. Huxley『ダーウィン仮説』 - 古代ギリシャには, 市民が機械を使う職業に従事することを禁じた都市国家があったということを, 我々はソクラテスを典拠として知っている.
We have it on the authority of Socrates that some city‐states in ancient Greece forbade their citizens to engage in occupations using machinery. - 研究社 新和英中辞典 - 『初会金剛頂経』は金剛界曼荼羅の典拠となる経典で、真言宗や天台宗では密教の「即身成仏」の原理を明確に説いているとしている。
"Shoe Kongocho-kyo" is a sutra (or sacred book) used as a reference for Diamond World Mandala, and within the Shingon sect and Tendai sect, it is said to clearly explain the principles of 'Sokushin-Jobutsu' (Attaining Buddhahood with the Present Body) in Esoteric Buddhism. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 上記の解釈に対し、『涅槃経』優位における解釈では、「秋収冬蔵」の典拠はその通りであるが、恣意的に前の文脈を省略しており、そのためにまったく逆の解釈がなされている、とする。
Those who support interpretations that place greater emphasis on the independent value of "the Nirvana Sutra" argue that the paragraph about 'harvesting in fall for winter storage' is correctly cited from the Nirvana Sutra but that his interpretation deliberately omits the statement preceding the paragraph, thereby giving rise to a serious misunderstanding. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 更に鎌倉時代後期に入ると武家側と対抗するために寺社を本所とする荘園の一円支配が強化され、荘園における本所法の典拠として本所である寺院の寺院法が用いられた。
Furthermore, in the late Kamakura period, temples tightened the control as honjo (proprietor or guarantor of manor) over the shoen and its surrounding areas to rival samurai, and as the rules of honjo, Jiin-ho were introduced, providing the authority for a honjo law at shoen. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 1980年代になって、硯友社文学全体の再評価の中で、典拠や構想についての研究が進み、アメリカの小説にヒントを得て構想されたものであるという説が有力になった。
In the 1980s, the whole literary works published by Kenyu-sha Company were revaluated, and the study of the souces and ideas for those novels was developed; as the result, a theory became dominant that this novel was based on American novels. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 『茶経』の「茶者南方嘉木」を典拠とする場合は「なんぽうろく」となるが、著者である南坊宗啓の名であるとする場合は「なんぼうろく」と濁音になる。
If a sentence in "Cha Jing"(The Classic of Tea) saying 'Tea is a good tree in the south ("nanpo," written as 南方)' is deemed to be the source, the pronunciation should be 'Nanporoku'; if it is deemed to come from Sokei NANBO (written as 南坊), the author's name, the pronunciation should be 'Nanboroku' with a voiced consonant. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 特定の典拠となった作品は不明であるが、『続古事談』に見える源師房家での歌合における平棟仲の逸話などから創作されたとも想像される。
Although a specific source is unknown, it is speculated that the story can be based on the anecdotes of TAIRA no Munenaka from "Zoku Koji Dan"(narrative in Kamakura period), in which a poetry contest hosted by MINAMOTO no Morofusa was portrayed. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 『日本書紀』の上記の箇所に、『釈日本紀』は調淡海や安斗智徳の日記を典拠に注記して、「石次は兵が起こるのを見て逃げかえった」と記す。
Adding to the descriptions above which appears in the "Nihonshoki" (Chronicles of Japan), "Shaku Nihongi," an annotated text of the Nihon Shoki, also says, "Iwatsugi fled as soldiers of the enemy camp rose," citing diaries of TSUKI no Oumi and ATO no Chitoko. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 小辺路の呼称を確認できる最古の史料は寛永5年(1628年)に編纂された笑話集『醒睡笑』巻一に収められた次の小話で、小辺路の読み方(こへち)の典拠もここである。
The oldest historical material that confirms the name 'Kohechi' is a story collected in "Seisuisho" (volume 1) which was a collection of comical stories compiled in 1628, and this pronunciation 'kohechi' (小辺路) is derived from it. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - ぼくがサッカーをやるとき、あるルールがぼくの行動を規定していて、ぼくが何をでき、何をできないかを教えてくれ、ぼくのサッカーを評価する(ルールブックが進め方の典拠なんだ)。
When I play soccer, certain rules define my activities, tell me what I can and cannot do, and evaluate my success (the rule book is my authority for how to proceed). - Ian Johnston『科学のカリキュラムで創造説?』 - 五仏(五智如来)と五大明王については日本国内に他にも造像例が多数あるが、金剛波羅蜜、金剛薩埵、金剛宝菩薩、金剛法菩薩、金剛業菩薩の組み合わせを五大菩薩として安置した例は他にほとんど知られず、その典拠は明らかでない。
Many Gobutsu (Gochi-nyorai) and Godai Myoo are seen throughout Japan but Godai Bosatsu which combine Kongouharamitsu, Kongosatta, Kongoho Bosatsu, Kongoho Bosatsu and Kongogo Bosatsu are only rarely enshrined at temples other than To-ji Temple and its authority is also unknown. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 美濃国の斎藤龍興との戦いのなかで、墨俣一夜城建設に功績を上げた話が有名だが、『武功夜話』などを典拠とするこのエピソードは当時の史料に関係する記述がなく江戸時代の創作であるとする説が強い。
There is a famous episode that he achieved to construct Sunomata Castle in one night in the middle of the battle with Tatsuoki SAITO of Mino province; this episode was described in 'Buko-yawa' and others, but there is no description of historical data in the document, so it is considered to be a fiction in Edo Period. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 3月10日、三成は家康の次男・結城秀康に守られて、佐和山城に帰城した(この事件時、三成が単身で向島の家康の屋敷に難を逃れたとする書物が多いが、これらの典拠となっている資料は明治期以降の「日本戦史・関原役」などである)
Mitsunari returned to Sawayama Castle guarded by the Ieyasu's second son, Hideyasu YUKI, on March 10 (some documents state that Mitsunari escaped to Ieyasu's residence in Mukojima in this incident but their sources, such as "History of Japanese Warfare, Sekigahara-no-eki," were written after the Meiji period). - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - それに対し、中国、インド・ネパール、チベット・ブータン、モンゴル・ブリヤート・トゥバ・カルムイク等のユーラシア大陸諸国そして台湾など、他の大乗仏教圏諸国の教団・信者は、このような文献学の成果を受容せず、信仰を揺るがす問題となっていないという説があるが、その調査等に関する典拠は不明である。
There is, however, a theory that the religious organizations and believers of other Mahayana Buddhist countries such as the Eurasian states of China, Nepal, Tibet, Butan, Mongolia, Buryat, Tuva, Kalmyks and Taiwan do not accept this result of philology, which doesn't represent a major problem, but the reason for that theory isn't known. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
- 経済産業省
- Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.
- 特許庁
- Copyright © Japan Patent office. All Rights Reserved.
- Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
- 本サービスで使用している「Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス」はWikipediaの日本語文を独立行政法人情報通信研究機構が英訳したものを、Creative Comons Attribution-Share-Alike License 3.0による利用許諾のもと使用しております。詳細はhttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ および http://alaginrc.nict.go.jp/WikiCorpus/ をご覧下さい。
- 日英対訳文対応付けデータ
- この対訳コーパスは独立行政法人情報通信研究機構の集積したものであり、Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unportedでライセンスされています。
- 原題:”Creationism in the Science Curriculum?”
邦題:『科学のカリキュラムで創造説?』 - This work has been released into the public domain by the copyright holder. This applies worldwide.
本翻訳は Ian Johnston : Creationism in the Science Curriculum? を日本語訳したものです。
翻訳は http://www.mala.bc.ca/~johnstoi/essays/creationism.htm に基づいています。
なお、この文書は著者によりパブリック・ドメインとして公開されています。
Copyright on Japanese Translation (C) 2004 Ryoichi Nagae 永江良一
本翻訳は、原著作を明示し、かつこの著作権表示を付すかぎりにおいて、訳者および著者に一切断ることなく、商業利用を含むあらゆる形で自由に利用し複製し配布することを許諾します。翻訳の改変を行うことも許諾しますが、その場合は、この著作権表示を付すほか、著作権表示に改変者を付加し改変を行ったことを明示してください。
- 原題:”Creationism in the Science Curriculum?”
- 原題:”Darwinian Hypothesis”
邦題:『ダーウィン仮説』 - This work has been released into the public domain by the copyright holder. This applies worldwide.
Copyright on Japanese Translation (C) 2002 Ryoichi Nagae 永江良一
本翻訳は、この著作権表示を付すかぎりにおいて、訳者および著者に一切断ることなく、商業利用を含むあらゆる形で自由に利用し複製し配布することを許諾します。
改変を行うことも許諾しますが、その場合は、この著作権表示を付すほか、著作権表示に改変者を付加し改変を行ったことを明示してください。
- 原題:”Darwinian Hypothesis”