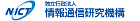「民族意識」を含む例文一覧(18)
- 民族意識.
race consciousness - 研究社 新英和中辞典 - 民族を構成している人が持つ自民族への帰属意識
constituents' sense of belonging to their own race - EDR日英対訳辞書 - 民族的な同一意識
a common identity that people of a culture or country share - EDR日英対訳辞書 - 民族の存続や発展を求める集団の意識
the mass consciousness toward a continuation of the race - EDR日英対訳辞書 - 同一の民族であるという意識を基盤として統一されている国家
a modern {nation}whose citizens consider themselves of a single nationality - EDR日英対訳辞書 - 体制に従おうとする意識は、この単一民族社会の本質的な要素である。
Conformity is an essential element of our homogeneous community. - Tatoeba例文 - デザインにおいて,他民族のもつ異国情緒を取り入れようという表現意識
the consciousness of expression to adopt the exotic mood of other races in design - EDR日英対訳辞書 - 体制に従おうとする意識は、この単一民族社会の本質的な要素である。
Conformity is an essential element of our homogeneous community. - Tanaka Corpus - また、国内では国学(学問)の普及にともなって民族意識がとみに高まった時代でもあった。
Within Japan, it was a time that ethnic consciousness was rising rapidly together with the spread of Kokugaku (study of Japanese literature and culture). - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 当時の世情として太田朝敷や沖縄県民は、大日本帝国の一員であり本土出身者と同じ日本民族だとの意識が広まりつつあったため、他の民族と同列に扱うことへの抗議でもあった。
At that time, the people in Okinawa were increasingly more conscious that those who lived in Okinawa, including Chofu OTA, were citizens of the Empire of Japan and are in the same ethnic group as the people on mainland Japan, so the protest was also meant to complain about being treated equally to the other ethnic groups. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - ベトナムにおける天下の概念は、13世紀の元寇を契機として民族意識が昂揚するとともに出現した。
In Vietnam, the notion of Tenka appeared in the 13th century when the ethnic consciousness was whipped up by the Mongol invasion. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - デジタルカメラにおいて、ユーザが意識することなく、自分の国や民族の好みにあった画像を得る。
To provide a digital camera, wherein an image congenial to a user's own country and a user's own nation is obtained without being conscious by a user. - 特許庁 - その後、大正・昭和と下るに連れて、日本のナショナリズム・民族主義が強まっていくと、大和魂の語には日本への強い意識が込めらるようになった。
Later, as Japanese nationalism and racism intensified during the Taisho and Showa periods, the word yamato-damashii began to connote a strong Japanese consciousness. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 蝦夷に統一アイデンティティーは無かったと解するか、日本との交渉の中で民族意識が形成されたであろうと想定するかは、研究者の間で意見が分かれている。
Opinions are varied among researchers regarding the interpretation of whether the Emishi lacked a unified identity or if their ethnic consciousness was formed while they were negotiating with Japan. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - なお、中国では出身地域によるライバル意識や、マレーシア・インドネシアでは複雑な民族構成、華僑と現地人との生活格差といった特有の問題もあるので留意が必要である。
The existence of problems specific to certain regions also needs to be noted. In China, for example, there exists a strong sense of rivalry according to where one is from, while in Malaysia and Indonesia, there are complex ethnic mixes and differences in living standards between ethnic Chinese and local people. - 経済産業省 - たとえばこの事件に関して、金城馨は、沖縄県の人々の抗議により、沖縄県民の展覧中止が実現したものの、他の民族の展覧が最後まで続いた点に注目し、「沖縄人の中にも、沖縄人と他の民族を同列に展示するのは屈辱的だ、という意識があり、沖縄人も差別する側に立っていた」と主張している。
For instance, Kaoru KINJO points out that while the display of the Okinawa people were successfully cancelled due to protest movement by residents in Okinawa, the exhibition of other ethnic groups continued to the last, and he insists "Even some of the people in Okinawa felt humiliated to have people from Okinawa displayed with other ethnic groups and they were also in a position to discriminate". - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 祖先の霊を祭る宗教行事だけではなく、国民的な休暇、民族移動の時期としての「お盆」としての側面があり、仏教的生活習慣を意識していない場合にはお盆(旧盆)は単なる夏休みになっているが、全国的に大多数の人が墓参りをするのが恒例である。
This 'Obon', as well as being a religious event to commemorate the souls of ancestors, has the air of a national holiday, with many people traveling around the country and, for those not aware of Buddhist practices, the Obon around August 15th is just a summer vacation, though most people throughout the country maintain the tradition of visting family graves. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - しかしこの宣言は、戦前戦中に「修身」の教科書などで国民が意識していた“日本国民は優秀な民族であり、世界の支配者たるべき立場にある”という概念を否定する文脈にあること、詔書の冒頭において「五箇条の御誓文」を掲げていることに見られるように、かならずしも従来の天皇のありかたそのものを否定するものでは無かったとする説もあった。
There was a theory stating that this declaration, seen as denying that, "Japanese people are a perfect race in position to rule the world," which was promoted to the people before and during the war through textbooks of 'Shushin' (moral training), etc., and having a 'Charter Oath of Five Articles' declared at the beginning of Shosho (Imperial edict), not necessarily denied completely the way the Emperor existed in the past. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
- Tatoeba例文
- Tatoebaのコンテンツは、特に明示されている場合を除いて、次のライセンスに従います:
 Creative Commons Attribution (CC-BY) 2.0 France
Creative Commons Attribution (CC-BY) 2.0 France
- Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
- 本サービスで使用している「Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス」はWikipediaの日本語文を独立行政法人情報通信研究機構が英訳したものを、Creative Comons Attribution-Share-Alike License 3.0による利用許諾のもと使用しております。詳細はhttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ および http://alaginrc.nict.go.jp/WikiCorpus/ をご覧下さい。
- 特許庁
- Copyright © Japan Patent office. All Rights Reserved.
- 経済産業省
- Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.
- TANAKA Corpus
- Tanaka Corpusのコンテンツは、特に明示されている場合を除いて、次のライセンスに従います:
 Creative Commons Attribution (CC-BY) 2.0 France.
Creative Commons Attribution (CC-BY) 2.0 France.