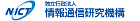「監護」を含む例文一覧(42)
- 監護の状況
Circumstances of Care - 日本法令外国語訳データベースシステム - 子の監護に関する事項
matters regarding custody of child - 法令用語日英標準対訳辞書 - 親権者の身上監護権
the rights of personal supervision of a person in parental authority - Weblio英語基本例文集 - 監護及び教育の権利義務
Right and Duty of Care and Education - 日本法令外国語訳データベースシステム - 離婚するにあたり、妻に共同監護を申し出る。
I applied for joint custody with my wife when we got a divorce. - Weblio英語基本例文集 - 離婚後の子の監護に関する事項の定め等
Determination of Matters regarding Custody of Child after Divorce etc. - 日本法令外国語訳データベースシステム - 認知後の子の監護に関する事項の定め等
Determination of Matters with Regard to Custody of Child after Affiliation etc. - 日本法令外国語訳データベースシステム - 子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し
Rescission of Adoption made without Consent of Person Who Cares for Child etc. - 日本法令外国語訳データベースシステム - 二 実父母が相当の監護をすることができること。
(ii) the natural parent(s) are capable of providing reasonable care for the child. - 日本法令外国語訳データベースシステム - 未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務
Rights and Duties regarding Personal Supervision of Minor Ward - 日本法令外国語訳データベースシステム - 親権者または後見人が、未成年者が自立した社会人となるように監護教育する権利義務を監護教育権という。
The right and duty that says parents or guardians must make minors have an education while caring for them so that they may become independent members of society is called the Right and Duty of Care and Education. - Weblio英語基本例文集 - 18才未満の児童を含む3人以上の児童を監護する,監護者に政府から月単位で支給される手当
an allowance paid monthly by the government to guardians who are responsible for three or more children, of whom one is a minor - EDR日英対訳辞書 - 2 この法律で「保護者」とは、少年に対して法律上監護教育の義務ある者及び少年を現に監護する者をいう。
(2) In this Act, the term "Custodian" refers to a person with a statutory obligation to have custody of and provide education to a Juvenile, or a person who has actual custody of a Juvenile. - 日本法令外国語訳データベースシステム - 彼は最初の時点から共同監護を望んでいたと述べた。
He said he had wanted joint custody from the start. - 旅行・ビジネス英会話翻訳例文 - 3 前二項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
(3) The rights and duties of parents beyond the scope of custody may not be altered by the provisions of the preceding two paragraphs. - 日本法令外国語訳データベースシステム - 第八百二十条 親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
Article 820 A person who exercises parental authority holds the right, and bears the duty, to care for and educate the child. - 日本法令外国語訳データベースシステム - 利便性とセキュリティ強度との両立を図ったワークスペースの監護システムを実現する。
To construct a supervision and protection system of a work space, which establishes compatibility between convenience and security strength. - 特許庁 - 2 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。
(2) If the family court finds it necessary for the child's interests, it may change who will take custody over the child and order any other proper disposition regarding custody. - 日本法令外国語訳データベースシステム - 政府の法的な監護下にある人を拘束するために使用される矯正施設(裁判を待っている被告人か服役している有罪となった人)
a correctional institution used to detain persons who are in the lawful custody of the government (either accused persons awaiting trial or convicted persons serving a sentence) - 日本語WordNet - 第六条 この法律で、保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
Article 6 The term "guardian" as used in this Act shall mean a person who has actual custody of a child, that is, a person who has parental authority, a guardian of a minor, or any other person. - 日本法令外国語訳データベースシステム - 第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
Article 766 (1) If parents divorce by agreement, the matter of who will have custody over a child and any other necessary matters regarding custody shall be determined by that agreement. If agreement has not been made, or cannot be made, this shall be determined by the family court. - 日本法令外国語訳データベースシステム - 第二十八条 保護者が、その児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、第二十七条第一項第三号の措置を採ることが児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県は、次の各号の措置を採ることができる。
Article 28 (1) In the case where a guardian abuses his/her child or extremely neglects the duty of custody of his/her child or in any other case where the guardian's exercise of the custody extremely harms the welfare of said child, when taking a measure set forth in Article 27 paragraph (1) item (iii) is contrary to the intention of a person who has parental authority or a guardian of a minor for the child, the prefectural government may take a measure set forth in any of the following items: - 日本法令外国語訳データベースシステム - 三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
(iii) The protector of the child (a person with parental rights, the guardian of the minor or any other individual, who is taking actual care of the child; the same shall apply hereinafter) or any person who has the child under his/her control. - 日本法令外国語訳データベースシステム - ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
c) The duty concerning the custody of a child under the provision of Article 766 of the Civil Code (including cases where applied mutatis mutandis pursuant to Article 749, Article 771 and Article 788 of said Code - 日本法令外国語訳データベースシステム - 2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。
(2) Where a person to be adopted is cared for by one of his/her parents and that parent does not have parental authority in relation to the person but cares for the person in accordance with Article 766, a legal representative shall obtain the consent of that parent before giving the consent referred to in the preceding paragraph. - 日本法令外国語訳データベースシステム - 第八百十七条の八 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。
Article 817-8 (1) In making a ruling of special adoption, the circumstances of not less than six months of the care given by the person(s) to become adoptive parent(s) over the person to become the adopted child shall be considered. - 日本法令外国語訳データベースシステム - 2 前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。
(2) The period in the preceding paragraph shall be calculated from the time of the application referred to in the provisions of Article 817-2; provided that this shall not apply if the circumstances of care are evident prior to the application. - 日本法令外国語訳データベースシステム - 三 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
iii) The duty concerning custody of a child under the provisions of Article 766 of the Civil Code (including the cases where it is applied mutatis mutandis pursuant to Article 749, Article 771 and Article 788 of the Civil Code - 日本法令外国語訳データベースシステム - 五 法務大臣が指定する施設、保護観察対象者を監護すべき者の居宅その他の改善更生のために適当と認められる特定の場所であって、宿泊の用に供されるものに一定の期間宿泊して指導監督を受けること。
(v) Staying in facilities designated by the Minister of Justice, the residences of persons who are to care for the probationers and parolees or other specific places that are considered suitable for improvement and rehabilitation and are offered as a place to stay for a prescribed period, and undergoing the instruction and supervision; - 日本法令外国語訳データベースシステム - 第八百十七条の五 第八百十七条の二に規定する請求の時に六歳に達している者は、養子となることができない。ただし、その者が八歳未満であって六歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。
Article 817-5 No person who has attained 6 years of age at the time of the application referred to in the provisions of Article 817-2 shall be adopted; provided that this shall not apply if he/she has not attained 8 years of age and has been continually cared for by a person to be an adoptive parent since before the child attained 6 years of age. - 日本法令外国語訳データベースシステム - 第八百十七条の七 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。
Article 817-7 A ruling of special adoption shall only be made if both parents of a person to be adopted are incapable or unfit to care for the child or there are any other special circumstances, and it is found that the special adoption is especially necessary for the interests of the child. - 日本法令外国語訳データベースシステム - 第六条の三 この法律で、里親とは、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)を養育することを希望する者であつて、都道府県知事が適当と認めるものをいう。
Article 6-3 The term "foster parent" as used in this Act shall mean a person, as found appropriate by the prefectural governor, who desires to take care a child without guardian or a child for whom the custody of his/her guardian is found inappropriate (hereinafter referred to as a "Aid-requiring Child"). - 日本法令外国語訳データベースシステム - 2 児童福祉施設の長又は里親は、入所中又は受託中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができる。
(2) Even in the case where a child admitted in a child welfare institution or entrusted to a foster parent has either a person who has parental authority or a guardian of a minor, the head of the child welfare institution or the foster parent may take measures necessary for welfare of the child with regard to his/her custody, education and disciplinary action. - 日本法令外国語訳データベースシステム - 第四百八十一条 前条の規定により刑の執行を停止した場合には、検察官は、刑の言渡を受けた者を監護義務者又は地方公共団体の長に引き渡し、病院その他の適当な場所に入れさせなければならない。
Article 481 (1) In cases where execution of a sentence is suspended pursuant to the provisions of the preceding paragraph, the public prosecutor shall transfer the sentenced person to either a person under obligation to care for him/her or to the head of the local government, and have such a person deliver the sentenced person to a hospital or any other appropriate location. - 日本法令外国語訳データベースシステム - 3 第一項の場合において、外国人が十六歳に満たない者であるとき又は疾病その他の事由により自ら上陸の申請をすることができないときは、その者に同行する父又は母、配偶者、子、親族、監護者その他の同行者がその者に代わつて申請を行うことができる。
(3) In the case referred to in paragraph (1), when the foreign national is under 16 years of age or is unable to apply for landing due to disease or for other similar grounds, his/her father or mother, spouse, child, relative, or legal guardian accompanying the foreign national or any other person accompanying the foreign national may file the application on behalf of the foreign national. - 日本法令外国語訳データベースシステム - 未成年者を監護する親権者として、テレビ番組の視聴時間やゲーム機での遊戯時間の長時間化に伴う影響が、子供である未成年者に及ぶことを防止することが容易に行えるテレビ視聴制限装置を提供すること。
To provide a television viewing limiting device which enables a person in parental authority who superintends minors, to easily prevent an influence caused by the increase for television program viewing or playing on a game machine, from being exerted upon minors being his or her children. - 特許庁 - 第三十八条 母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
Article 38 A maternal and child living support facility shall be a facility intended for admitting and protecting females without a spouse or females in equivalent circumstances and the children whose custody must be taken by those females and supporting their life to encourage their self-reliance, as well as intended for providing consultation and other assistance to those who have left there. - 日本法令外国語訳データベースシステム - 第二十五条の二 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、保護者に対し、少年の監護に関する責任を自覚させ、その非行を防止するため、調査又は審判において、自ら訓戒、指導その他の適当な措置をとり、又は家庭裁判所調査官に命じてこれらの措置をとらせることができる。
Article 25-2 The family court may take appropriate measures against the Custodian, if it is found necessary, including delivering an admonition, giving guidance etc., or order a family court probation officer to take these measures in the course of investigation or hearing, in order to raise awareness of responsibility of the Custodian for custody of the Juvenile and to prevent the Juvenile from committing delinquency. - 日本法令外国語訳データベースシステム - 第五十九条 保護観察所の長は、必要があると認めるときは、保護観察に付されている少年(少年法第二条第一項に規定する少年であって、保護観察処分少年又は少年院仮退院者に限る。)の保護者(同条第二項に規定する保護者をいう。)に対し、その少年の監護に関する責任を自覚させ、その改善更生に資するため、指導、助言その他の適当な措置をとることができる。
Article 59 The director of the probation office may, if deemed necessary, give guidance or advice, or take other suitable measures for parents and guardians (who shall be the parents and guardians specified in paragraph (2) of Article 2 of the Juvenile Act) of juveniles under probation (who shall be limited to the juveniles specified in paragraph (1) of said Article, being the juvenile under probation or the parolee from the juvenile training school) for the purpose of having them realize their responsibility regarding the care of such juveniles and to contribute to the improvement and rehabilitation of the juveniles. - 日本法令外国語訳データベースシステム - 第二十三条 都道府県等は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者及び児童を母子生活支援施設において保護しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、適当な施設への入所のあつせん、生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)の適用等適切な保護を加えなければならない。
Article 23 (1) In the case where a guardian in the area of responsibility of the Welfare Office established by any of the Prefectures, etc. is a female without spouse or a female in equivalent circumstances and there is lack in welfare of the child whose custody must be taken by her, the Prefecture, etc., shall, when said guardian applies, take into protective custody the guardian and the child in a maternal and child living support facility; provided, however, that, when there is any unavoidable reason, the arrangement for admission into another appropriate facility, the application of the Public Assistance Act (Act No. 144 of 1950) or any other adequate aid shall be implemented. - 日本法令外国語訳データベースシステム - 第二十四条 市町村は、保護者の労働又は疾病その他の政令で定める基準に従い条例で定める事由により、その監護すべき乳児、幼児又は第三十九条第二項に規定する児童の保育に欠けるところがある場合において、保護者から申込みがあつたときは、それらの児童を保育所において保育しなければならない。ただし、付近に保育所がない等やむを得ない事由があるときは、その他の適切な保護をしなければならない。
Article 24 (1) In the case where a guardian' working or illness or any other reasons prescribed by a Municipal Ordinance in accordance with the standards specified by a Cabinet Order causes lack in daycare of an infant, a toddler or a child prescribed in Article 39 paragraph (2) whose custody must be taken by the guardian, a municipal government shall, when the guardian applies, provide daycare to those children in a nursery center; provided, however, that other adequate aid shall be provided when there is any unavoidable reason such as non-existence of an adjacent nursery center. - 日本法令外国語訳データベースシステム - 2 前項第一号及び第二号ただし書の規定による措置の期間は、当該措置を開始した日から二年を超えてはならない。ただし、当該措置に係る保護者に対する指導措置(第二十七条第一項第二号の措置をいう。以下この条において同じ。)の効果等に照らし、当該措置を継続しなければ保護者がその児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他著しく当該児童の福祉を害するおそれがあると認めるときは、都道府県は、家庭裁判所の承認を得て、当該期間を更新することができる。
(2) The period for a measure taken pursuant to the provision of item (i) and the proviso of item (ii) of the preceding paragraph shall not exceed 2 years from the date of commencement of said measure; provided, however, that the prefectural government may renew said period with approval from the family court, when it is found that the guardian is likely to abuse the child, extremely neglect the custody of the child, or cause any other harm to the welfare of said child, in light of effects, etc. of the guidance to the guardian pertaining to the referenced measure (which shall mean the guidance set forth in Article 27 paragraph (1) item (ii); the same shall apply hereinafter in this Article) unless the referenced measure is continued. - 日本法令外国語訳データベースシステム

- ※この記事は「日本法令外国語訳データベースシステム」の2010年9月現在の情報を転載しております。

- ※この記事は「日本法令外国語訳データベースシステム」の2010年1月現在の情報を転載しております。
- 特許庁
- Copyright © Japan Patent office. All Rights Reserved.