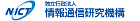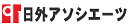「鳥の子」を含む例文一覧(94)
1 2 次へ>- 鵞鳥の子
a gosling - 斎藤和英大辞典 - 白鳥の子
a cygnet - 斎藤和英大辞典 - 鳥の子餅
Torinoko-mochi (child-bird mochi) - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 紀田鳥の子。
He is the son of KI no Tadori. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 鳥の子紙という和紙
a type of Japanese paper called 'torinokogami' - EDR日英対訳辞書 - 薄手の鳥の子紙
thin Japanese 'torinoko' paper - EDR日英対訳辞書 - 厚い鳥の子紙
thick, smooth Japanese paper called 'torinoko' - EDR日英対訳辞書 - 鳥の子が巣から落ちておった
A young bird had fallen out of the nest. - 斎藤和英大辞典 - 非常に薄くすいた鳥の子紙
very thin Japanese tissue paper - EDR日英対訳辞書 - 雲紙という,鳥の子紙
a kind of Japanese paper ['torinoko' paper] called {'cloud paper'} - EDR日英対訳辞書 - 白くて薄い鳥の子紙
a type of Japanese paper that is thin, white and smooth - EDR日英対訳辞書 - 漆糸という,鳥の子紙の撚り糸
a type of Japanese silk twine, called 'urushiito' - EDR日英対訳辞書 - 鳥の子類には、間似合紙、色間似合紙、屏風紙、雲屏風紙、鳥の子紙、五色鳥の子紙、雲鳥の子紙、広鳥の子、土入り鳥の子紙などがある。
The torinoko type includes maniai-shi, colored maniai-shi, paper for folding screens, cloud-patterned paper for folding screens, torinoko paper, five-colored torinoko paper, cloud-patterned torinoko paper, wide torinoko paper and soil-contained torinoko paper. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 現在、越前国では手漉き紙を「本鳥の子」といい、機械漉き紙を「鳥の子」という。
Today, in the former Echizen Province a handmade paper is called 'hon-torinoko' and machine-made paper is called 'torinoko.' - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - このほかにも、全て機械漉きの量産されているものに、「上新鳥の子」と「新鳥の子」がある。
Besides, the other mass produced products completely machine-made are 'joshin-torinoko' (the upper class of new torinoko) and 'shin-torinoko' (new torinoko). - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 名塩鳥の子の漉き方は、泥入り鳥の子であるために、留め漉きを特徴としている。
The characteristic of Najio torinoko paper is Tome-suki because of soil-contained torinoko. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 鳥の子紙という和紙に塗った漆の箔
a smooth Japanese paper called 'torinokogami' - EDR日英対訳辞書 - 氷襲という,白い鳥の子紙を2枚合わせたもの
two sheets of Japanese 'torinoko' paper - EDR日英対訳辞書 - 帖紙:紅色の鳥の子紙
Tatogami (pieces of paper kept inside the bosom): Deep red torinokogami (smooth and glossy Japanese paper). - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 同様に「薄様」についても説明があり、鳥の子と区別していることから、鳥の子は厚手の雁皮紙(がんぴし)を指していたと考えられる。
Since there is also a description of 'usu-yo' (thin torinoko-colored paper) distinguished from torinoko, it seems that torinoko referred to thick ganpishi (thick Japanese paper made from fibers taken from the bark of a clove-like bush). - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 近世の『和漢三才図絵』には、鳥の子に関して「俗に言う、厚葉、中葉、薄葉三品有り」と記して、すべての雁皮紙を鳥の子と呼んでいる。
In the "Wakansansaizue" (a Japanese encyclopedia made in recent times), torinoko was described as 'being classified into three kinds of atsu-yo, chu-yo (medium torinoko paper), and usu-yo' and all ganpishi were called torinoko. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 鎌倉末期から鳥の子の名称が一般化し、近世に入ると雁皮紙(がんぴし)はすべて鳥の子紙と呼ぶようになった。
The name torinoko became generalized since the end of the Kamakura period, and all ganpishi came to be called torinoko in the recent times. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 漉き染めした色鳥の子は色数も豊富で、一般に流通している高級な鳥の子の代表としてさまざまな住宅に使用されている。
The iro-torinoko (colored torinoko) of suki-zome (mixing dyed fibers when paper-making) has a variety of colors and has been used for various houses as a major high quality torinoko which is generally distributed. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 「上新鳥の子」は、鳥の子の普及品で、全て機械漉きのため比較的価格が安く均質なため、一般住宅に用いられている。
Joshin-torinoko is a popular edition of torinoko and because of its low price and homogeneity it is used for conventional homes. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - から紙の地紙はもともと檀紙(楮紙)や鳥の子紙(雁皮紙)が使われ、「京から紙」は主に鳥の子紙と奉書紙が用いられた。
For the basal paper of karakami the dan-shi (Japanese paper of high quality made from mulberry trees) (a kind of kozo paper) and torinoko paper (a kind of ganpishi) were originally used, and for 'Kyo karakami' torinoko paper and hoshogami were used. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 現在では、量産可能な機械漉きの「鳥の子」が主流を占めている。
Today, the machine-made 'torinoko,' which enables mass production, is mainly produced. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 近世に入ると雁皮紙はすべて鳥の子紙と呼ぶようになった。
In the recent times, all ganpishi were called torinoko paper. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - この鳥の子紙に木版で紋様を施したのが「から紙」である。
Karakami' refers to torinoko paper on which patterns are printed by woodblock. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 鳥の子供の姿に似せてずん胴のひょうたん型に成形した餅。
Mochi shaped into a gourd-like shape having no narrow portion to make the shape resemble the shape of a child bird. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - これらの名塩鳥の子土(泥土)には、東久保土(白色)、天子土(卵色)、カブタ土(青色)、蛇豆土(茶褐色)などの名があり、一種または二種を混合して漉きあげ、五色鳥の子、染め鳥の子などとも呼ばれた。
These soils for torinoko in Najio have names such as Tokubo soil (white), Tenshi soil (天子土) (whitish brown), Kabuta soil (blue), and Jato soil (ginger), and paper was made with one or two soils that was called five-colored torinoko or dyed torinoko. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - この雁皮紙が鳥の子と称されるようになるのは、南北朝時代(日本)頃からである。
This ganpishi became to be called torinoko since the period of the Northern and Southern Courts (Japan). - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 近世にはいると、「薄様」の名も消えて、雁皮紙をすべて鳥の子と呼ぶようになる。
In the recent times, the term 'usu-yo' disappeared and all ganpishi came to be called torinoko. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - さらにすべて手漉きで、漉き込み模様を付けたものを、「本鳥の子漉き模様紙」という。
Moreover, all handmade paper with a pattern added is called 'genuine patterned torinoko paper.' - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 手漉きの本鳥の子紙は、現在では非常に高価なため生産量も少い。
The handmade hon-torinoko paper is very expensive and its production is small at present. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 近年の家庭用の糊付きふすま紙も殆どはこの「新鳥の子」を使用している。
Shin-torinoko' is used for almost all domestically glued fusuma paper. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - このことは、名塩鳥の子の紙質が一段ときめ細やかになるもとになっている。
This is why the quality of Najio torinoko paper is smoother. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 間似合紙は五枚ないし六枚てで足り、間似合唐紙とか間似合鳥の子ともいわれた。
On the other hand, only five or six maniai-shi were enough to cover fusuma-shoji, and its was also called maniai karakami or maniai torinoko. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - この雁皮紙が鳥の子と称されるようになるのは、南北朝時代頃からである。
This ganpishi came to be called torinoko during the period of the Northern and Southern Courts. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 太平洋戦争後には、越前鳥の子や輪転機による多色刷りのふすま紙に押されて衰滅した。
After the Pacific War, it declined because of the rise of Echizen torinoko and multicolored fusuma paper made by rotary presses. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 鳥の子の名の由来については、文安元年(1444年)成立の『下学集』では、「紙の色 鳥の卵の如し 故に鳥の子というなり」と説明している。
In the "Kagaku-shu" (a Japanese dictionary made in the Muromachi period) written in 1444, the origin of the name of torinoko (literary, a child of a hen) was described as 'The color of paper looks like that of an egg of a hen, so it was called torinoko.' - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 伝統的な手漉き越前和紙の「本鳥の子」は、高級襖紙の代名詞であり時間が経つほどに鳥の子の肌は独特の風合いを保ち、むしろ新しいものよりも上品な肌合いになる。
The 'hon-torinoko,' a traditional handmade Echizen paper, is a synonymous with high-quality fusuma paper, which keeps its unique taste and rather, exhibits a more refined touch as it ages. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 機械漉きの鳥の子でも、紙料は本鳥の子と同様の靱皮(じんぴ)繊維の楮や三椏を使ったものからパルプを使ったものまで品質もさまざまである。
There are various kinds of machine-made torinoko with various qualities, ranging from those made of kozo and mitsumata of bast fiber to those made of wood pulp. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 名塩でも弥右衛門を名乗り、優れた越前の鳥の子の製紙技術を指導し、さらに改良や普及に尽力して、その業績を高く評価されて名塩鳥の子の始祖と讃えられるようになったと思われる。
It seems he also used the name Yaemon in Najio, taught the superior technique of torinoko manufacturing in Echizen, and made efforts in improving and disseminating it, so his achievements were highly esteemed and he was admired as the originator of Najio torinoko. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 「名塩鳥の子紙」の銘柄が、上方の取引市場に出るのは寛永15年(1638年)からといわれ、近世初期には名塩鳥の子の名で上方市場の有力商品となっていた。
It is said that a brand of 'Najio torinoko paper' appeared on the market in Kamigata (Kyoto and Osaka area) in 1638, and it became a best-selling item there like the name of Najio torinoko in the early period of recent times. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 岡田渓誌著『摂陽群談』(元禄14年(1701年)刊)には、「名塩鳥の子土、同所にあり。この土を設け鳥の子紙に漉き交え美を能くす」とある。
In the "Setsuyo gundan" (a topography of Settsu province)" written by Keishi OKADA (published in 1701), there is the description; 'There is a special soil for torinoko paper in Najio. This soil is mixed with torinoko paper during the paper-making process and it makes the paper more beautiful.' - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 襖障子は、表面仕上げに鳥の子紙を貼り、その上に金箔を貼りその上から極彩色の岩絵の具で絵柄を描くか、鳥の子の地肌に直接彩色あるいは墨で絵を描いたものを指した。
Fusuma-shoji referred to shoji on which torinoko paper was pasted for finishing the surface, patterns were drawn by richly colored mineral paints on an applied gold foil over it or the pictures were drawn in colors or with Sumi directly on the surface of the torinoko paper. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 襖に白鳥の子を張るという伝統は今日にも引き継がれており、格式の高い料亭や旅館にも使われており、皇居の和室の襖も白の鳥の子が張られているという。
The tradition to paste white torinoko on fusuma has been continued until now in first-class Japanese restaurants and Japanese-style hotels of high social status, and it is said that white torinoko is pasted on the fusuma of Japanese-style room in the Imperial Palace. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 両集ともに厚様の説明が欠けていることから、平安時代から和紙(がんぴし)の厚様を鳥の子と呼んでいたと考えられる。
Because there are no explanations about atsu-yo (thick torinoko-colored paper) in both dictionaries, it seems that the atsu-yo of ganpishi had been called torinoko since the Heian period. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 鳥の子紙は、主に詠草(えいそう)料紙(りょうし)や写経料紙(りょうし)に用いられ、時には公文書にも使用された。
The paper of torinoko had been mainly used as ryoshi (paper for writing) for eiso (paper on which a tanka or a haikai is written) and hand-copying of sutras, and sometimes used for official documents. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - このほかに伊豆国・美濃国・土佐国も雁皮紙(がんぴし)の産地として知られているが、「鳥の子」の紙名は用いていない。
Besides, Izu, Mino, and Tosa Provinces are also famous producing districts of ganpishi, where the name of 'torinoko' is not used. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
- Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
- 本サービスで使用している「Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス」はWikipediaの日本語文を独立行政法人情報通信研究機構が英訳したものを、Creative Comons Attribution-Share-Alike License 3.0による利用許諾のもと使用しております。詳細はhttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ および http://alaginrc.nict.go.jp/WikiCorpus/ をご覧下さい。