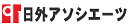「亀鑑」を含む例文一覧(62)
1 2 次へ>- 軍人の亀鑑
He is a model soldier―a model officer. - 斎藤和英大辞典 - 武士の亀鑑
He is a mirror of Japanese knighthood. - 斎藤和英大辞典 - 女子の亀鑑
She is a model of womanhood. - 斎藤和英大辞典 - 淑徳の亀鑑
She is a paragon of virtue―a pattern of female honour―the soul of honour. - 斎藤和英大辞典 - 貞節の亀鑑だ
She is a pattern of female honour―a paragon of feminine virtue. - 斎藤和英大辞典 - 貞操の亀鑑だ
She is a pattern of female honour―a paragon of feminine virtue. - 斎藤和英大辞典 - その忠節、後世の亀鑑たらん
His loyalty will be a model to future generations. - 斎藤和英大辞典 - 彼女は淑徳の亀鑑である
She is a paragon of virtue―a pattern of female honour―the soul of honour. - 斎藤和英大辞典 - なお、池田亀鑑により2種類に区別された。
It was divided into two groups by Kikan IKEDA. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 源氏物語大成 中央公論社 池田亀鑑編
Kikan IKEDA, ed., "Genji monogatari taisei," Chuo Koronsha. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 写本については池田亀鑑の説では以下の3種類に分けられるとされる。
According to the theory of Kikan IKEDA, the manuscripts are divided into three groups. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 『校異源氏物語』(全4巻)池田亀鑑(中央公論社、1942年)
"The Tale of Genji Match-up" (4 vols. complete) Kikan IKEDA (Chuokoron-sha, Inc., 1942) - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 『源氏物語大成』(校異編)池田亀鑑(中央公論社、1953年-1956年)
"The Tale of Genji Match-up Corpus" (Match-up edition) Kikan IKEDA (Chuokoron-sha, Inc., 1953-1956) - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 『源氏物語大成校異篇』池田亀鑑編(中央公論社、1953年〜)
"Genji Monogatari Koi hen" edited by Kikan IKEDA (CHUOKORON.SHA INC., 1953 -) - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 池田亀鑑は別本の中には次のようなものが含まれるとしている。
Kikan IKEDA considered that the following manuscripts were classified into Beppon. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 『源氏物語大成校異篇』池田亀鑑編(中央公論社、1953年〜)
"Genji monogatari taisei Koi hen" edited by Kikan IKEDA (Chuo Koronsha, since 1953) - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - その結果は池田亀鑑により『校異源氏物語』および『源氏物語大成 校異編』に結実した。
As a result, Kikan IKEDA published "The Tale of Genji Match-up" and "The Tale of Genji Match-Up Corpus." - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 『源氏物語』日本古典全書(全7巻)池田亀鑑著(朝日新聞社、1946年~1955年)
"The Tale of Genji," A Complete Book of Japanese Classic (seven volumes, complete) written by Kikan IKEDA (The Asahi Shinbun Company, 1946 to 1955) - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 林和比古『枕草子の研究』によれば自説と過去の契沖、折口信夫、池田亀鑑などの研究者を挙げている。
"A study of the Pillow Book" written by Kazuhiko HAYASHI mentions his own view and some other past scholars' names such as Keichu, Shinobu ORIKUCHI, and Kikan IKEDA. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 池田亀鑑は諸本の研究の上、120種以上に及ぶ写本群から自筆本再構のために証本を選んだ。
Kikan IKEDA chose the Shohon (premised book) among more than 120 versions of the manuscript in order to reconstruct the original work. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - そのため、池田亀鑑は当初河内本系統の写本を元に学術的な校本を作ろうとし、一度は完成間近まで作業は進行した。
So, at first, Kikan IKEDA tried to make an academic variorum edition based on the Kawachi-bon line manuscripts, and the work was about to be finished once. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 源氏物語大成(げんじものがたりたいせい)とは、池田亀鑑編著による源氏物語の校異を中心にした研究書である。
Genji monogatari taisei (Comprehensive Study of The Tale of Genji) is a study of The Tale of Genji written and compiled by Kikan IKEDA, and it mainly dealt with the differences among the various versions of text. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 最終的にこの事業は大正15年(1926年)4月に、当時若手の研究者として将来を期待されていた池田亀鑑に委嘱されることになった。
In the end, Kikan IKEDA, a promising young scholar at that time, was commissioned to do the work in April, 1926. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 『校異源氏物語』の完成をもって芳賀矢一記念会が解散したことにより、これ以後は形式的には池田亀鑑個人の事業になる。
The Memorial Association of Yaichi Haga dissolved after completion of "Koi Genji monogatari," so the works hereafter were formally Kikan IKEDA's individual project. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 池田亀鑑は続いて第三期の作業として本来の目標であった「源氏物語古注集成」の編纂作業にとりかかったとされている。
It is considered that as the third period of his work, Kikan IKEDA set about compiling 'a collection of old annotations on The Tale of Genji,' which was his original goal. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 池田亀鑑は、約300点、冊数にして約15,000冊の写本を調査し、写本を撮影したフィルムは約50万枚に及ぶとされている。
Kikan IKEDA is said to have investigated about 300 manuscripts, or 15,000 books of manuscript, and the number of films he used reached about five hundred thousand. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - これは、異なる系統の本文を安易に比較校合の対象とするべきではないとする池田亀鑑の考えを反映したものであると見られる。
It is considered that this reflected the idea of Kikan IKEDA, that the texts in the different lines should not been compared and collated easily. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 本書の成立には多くの研究者の協力があったほか、池田亀鑑の父宏文をはじめとする家族の協力もあったとされている。
It is said that many scholars cooperated with Kikan IKEDA in making this book, and his family, especially his father Hirofumi, helped him with the work. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - そのため、池田亀鑑に対する精神的な側面での助力や単純な労力的な作業の手伝いに限られているとする見方もあった。
Therefore, some people thought that it suggested just mental support for Kikan IKEDA and help in simple but laborious work. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 「2百5,6十種の伝本を調査した」とする池田亀鑑は「発達史的観点」から源氏物語系図を以下の3つに分けた。
Kikan IKEDA, who 'investigated 250 to 260 kinds of existing manuscripts,' classified genealogies of The Tale of Genji into the following three groups 'in terms of development.' - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 池田亀鑑はこれを総角(源氏物語)を椎本の並びの巻にしてしまい巻序を示す数字を書かなかった。
Kikan IKEDA surmises that this was because the compiler considered the 'Agemaki' (Trefoil Knots) chapter a 'parallel chapter' to the 'Shigamoto' (Beneath the Oak) chapter and therefore did not give it a number. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 4巻ものの劇映画『都に憧れて』、2巻ものの短篇劇映画『忠孝の亀鑑小楠公』の脚本を金森に書かせて監督させた。
He had KANAMORI script and direct 4 volumes of narrative film titled "Yearning for the City," and 2 volumes of short narrative film titled "Tadataka no Kikan Shonanko." - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - しかし、池田亀鑑の弟である池田晧が普及版の月報において明らかにしたところによれば、校異編において使われている校異の表記方法はいくつかの試行錯誤の末池田晧の提案を池田亀鑑が採用したものであることなどを始めとして、『源氏物語大成』の成立に係わる極めて重要な部分にまでその助力が及んでいることが明らかになった。
However, according to what Kikan IKEDA's younger brother, Akira IKEDA, revealed in the monthly bulletin of a popular edition, the family cooperated with him even in the quite important work of completing "Genji monogatari taisei," for example, Kikan IKEDA tried and failed the way of describing the differences in the book of comparison, and then he finally adopted Akira IKEDA's suggestion. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 藤原定家の記した「奥入」には、この位置に「輝く日の宮(かかやくひのみや)」という帖がかつてはあったとする説が紹介されており、池田亀鑑や丸谷才一のようにこの説を支持する人も多い。
A commentary of 'Okuiri' written by FUJIWARA no Sadaie introduces the opinion that there once was a chapter of 'Kakayakuhi no Miya' in this part, and many people such as Kikan IKEDA and Saiichi MARUYA agree with that opinion. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 池田亀鑑は集められた多くの写本を「青表紙本系」と「河内本系」の2つに分け、それに属さない写本を「別本」として1つにまとめ、3種類の系統に分けた。
Kikan IKEDA classified many gathered manuscripts into three lines: the 'Aobyoshibon line,' 'Kawachibon line' and 'Beppon,' a group of manuscripts that don't belong to either of the aforementioned lines. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - わけても、原本を忠実に写したとされる青谿書屋本などをもとにして池田亀鑑がなした『古典の批判的処置に関する研究』(1941年)にいたってほとんど完成するに至った。
Above all, Kikan IKEDA wrote "A Study on Critical Dealing with the Classics" (1941), concerning himself with the Seikeishookubon, which is said to have been copied true to the original manuscript, and brought his study near to completion. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 実際、「猿蓑」は芭蕉にとっては、末代の亀鑑となるべき集であり、その指導もそれまでの撰集とは異なる態度で助言したと想像されている。
In fact, Basho considered that 'Sarumino' was a collection that was to be a good example for posterity, so it is imagined that he advised and instructed his disciples more enthusiastically than ever. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - わびさびのもっとも円熟した時期の集であり、真に幽玄閑寂の風をあらわし、発句、連句ともに天下の亀鑑であるとされる。
It is a collection compiled while the idea of wabi (taste for the simple and quiet) and sabi (tranquility) matured most, expressing yugen (subtle and profound beauty) kanjaku (quiet), so both hokku and renku in the collection are the best models in the whole country. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - こうしたことを理由として古くは室町時代の注釈書である『源氏物語聞書』、近代に入ってからは与謝野晶子により、さらには池田亀鑑らによってしばしば後挿入説・後記説が唱えられている。
It is one of the reasons why the Theory of Later Insertion or Postscript has been advocated from ancient times by many people and books, including "Genji monogatari kikigaki" (commentaries in the Muromachi period), Akiko YOSANO, Kikan IKEDA, and others. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 大島雅太郎は三井合名会社の理事をつとめていたことなどから豊かな財力を背景にして池田亀鑑を顧問にして多くの貴重な書籍を集めていた。
Masataro OSHIMA, serving as a director of Mitsui Gomei Kaisha, used his prodigious wealth to engage Kikan IKEDA as an advisor and collected many valuable books and manuscripts. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 池田亀鑑は、本写本を「青表紙本中最も信頼すべき一証本であって、その数量において、またその形態・内容において稀有の伝本である」とした。
Kikan IKEDA praised the manuscript as 'the most reliable shohon (a verified text) among the Aobyoshi-bon line and a rare book in its volumes, form and contents.' - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - また、本写本の初音帖の本文については池田亀鑑によって「青表紙本ではなく別本である」とされ、「源氏物語大成」の底本への採用を見送られた。
As for the text of the chapter "Hatsune" in the Oshima-bon manuscript, Kikan IKEDA considered it as 'not Aobyoshi-bon but Beppon,' and it was not adopted in the original text of the 'Genji monogatari taisei.' - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 池田亀鑑は1926年に東京帝国大学文学部国文学科を卒業し、1956年12月に死去したため、学者としての、研究生活のほぼ全期間を本書を作成する仕事に捧げたことになる。
Kikan IKEDA graduated from Department of Japanese Literature, Faculty of Letters, Tokyo University in 1926, and passed away in December, 1956, so he devoted almost whole life of studying as a scholar to completing the work. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - また池田亀鑑の弟である池田晧は、「底本は数回変更された。」と語っており、底本が変更されたのは河内本系統の写本から大島本に変更された1回だけではないことになる。
Kikan IKEDA's younger brother, Akira IKEDA, told that 'the original text was changed several times,' which suggests that he changed the original text more than one time, in which the change was made from the Kawachi-bon line manuscript to the Oshima-bon. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - しかし、東海大学附属図書館館長であった原田敏明が池田亀鑑の妻の兄であった関係等からその管理を任されるようになった。
However, Toshiaki HARADA, a chief librarian of Tokai University Library, came to be in charge of the books because he was an older brother of Kikan IKEDA's wife and for other reasons. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 前にある巻の話に続く話の巻(縦の並び)と前にある巻の話と同じ時間帯の話の巻(横の並び)があるとする説(池田亀鑑などの説)
The opinion that there were chapters which were sequel to the previous chapter (vertical narabi) or had the same time setting as the previous chapter (horizontal narabi) (the opinion advocated by Kikan IKEDA and others). - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 「別本」の呼称は池田亀鑑により1942年(昭和17年)に出版された源氏物語の校本である「校異源氏物語」において初めて用いられたもので、後に「源氏物語大成」などにも採用されて広く普及することになった。
The name, 'Beppon,' was first used in 'Koi Genji monogatari,' a variorum of The Tale of Genji, published by Kikan IKEDA in 1942, and later it also came to be widely used in 'Genji monogatari taisei' (Comprehensive Study of The Tale of Genji), and so on. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - なお、古系図について、池田亀鑑は「九条家本」系統、「為氏本」系統、「正嘉本」系統の3系統に、後には「天文本」系統を加えて4系統に分類している。
Kikan IKEDA classified old genealogies into three groups of 'Kujoke-bon manuscript,' 'Tameuji-bon manuscript,' 'Shoka-bon manuscript,' and later added 'Tenbun-bon manuscript' to them, making four groups. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 池田亀鑑は、このような源氏物語年立が成立したことは源氏物語古系図の成立と併せて当時の人々が源氏物語に対して研究的態度で接するようになったことの現れであるとしている。
Kikan IKEDA says that the appearance of the 'Genji monogatari toshidate,' together with the appearance of the 'Genji monogatari kokeizu' (old genealogies on the Tale of Genji), indicates that people at that time were beginning to look at the Tale of Genji from a scholarly point of view. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス - 池田亀鑑は源氏物語の写本にこの「奥入」があるかどうかを写本が藤原定家の証本の流れを汲む青表紙本であるかどうかを判断する条件に挙げている。
Kikan IKEDA mentions that when judging whether a manuscript of the Tale of Genji is an Aobyoshi-bon manuscript, those that are descended from FUJIWARA no Sadaie's shohon, it is a requirement for the manuscript to have this 'Okuiri' in it. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
- Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
- 本サービスで使用している「Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス」はWikipediaの日本語文を独立行政法人情報通信研究機構が英訳したものを、Creative Comons Attribution-Share-Alike License 3.0による利用許諾のもと使用しております。詳細はhttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ および http://alaginrc.nict.go.jp/WikiCorpus/ をご覧下さい。