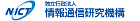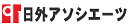| 意味 | 例文 (14件) |
鉄器時代の部分一致の例文一覧と使い方
該当件数 : 14件
弥生時代の道具類を材質から分類すると、大きく石器、木器・青銅器・鉄器・土器などに分けることができる。例文帳に追加
Tools used in the Yayoi period can be divided into materials, such as; stoneware, woodenware, bronze-ware, ironware, and earthenware. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
ただし、この時期の鉄器は鉄素材を半島から輸入して製作されており、列島で製鉄が見られるのは古墳時代後期以降と考えられる。例文帳に追加
However ironware during this period were made from iron imported from the peninsula and iron making in Japan Archipelago is said have started after the end of the Kofun period. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
北部九州、特に福岡市周辺地域では弥生時代中期前半までに鍛造技法による鉄器の生産が開始された。例文帳に追加
Ironware manufacturing by forging had started by the first half of the middle of the Yayoi period in northern Kyushu, especially in surrounding area of Fukuoka City. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
一方、同じ北部九州でも八女市などの周辺地域では弥生時代後期になっても鏨切りによる鉄器生産が一般的であった。例文帳に追加
On the other hand, ironware manufacturing by cold chisel cutting was common in surrounding area of Yame City, also in northern Kyushu, even at the end of the Yayoi period. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
ほか1階では鉄器など黒塚古墳出土品を展示して古墳時代の大和と黒塚古墳についてパネルで紹介している。例文帳に追加
On the first floor, there is also a display of artifacts, such as ironware, excavated from Kurozuka Tumulus with explanation panels to describe Kurozuka Tumulus as well as Yamato during the Kofun period (tumulus period). - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
瀬戸内地方でも、弥生時代後期までには鍛造による鉄器生産が伝播していたが、技術的には北部九州のそれよりも明らかに低い水準にあり、同時に鏨切りによる鉄器製作も普遍的に行われていた。例文帳に追加
Moreover, although ironware manufacturing by forging was introduced to the Setouchi region by the end of the Yayoi period, technology was clearly lower than that of northern Kyushu and ironware manufacturing by cold chisel cutting was practiced in general. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
一方、邪馬台国九州説では、弥生時代後期中葉以降に至っても瀬戸内地域では鉄器の出土量は北部九州と比べて明らかに少なく、また、鉄器製作技術は北部九州と比べて格段に低かった。例文帳に追加
For the Yamatai-Koku kingdom in Kyushu theory, on the other hand, the amount of ironware excavated from the Setouchi region even after the middle of the end of the Yayoi period was very limited when compared to northern Kyushu, and the level of ironware manufacturing technique was very low compared to northern Kyushu. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
弥生時代後期には、玄界灘沿岸地域の遺跡から鉄器が大量に出てくるが、瀬戸内海沿岸各地方や近畿地方の遺跡からはごくわずかしか出てこない。例文帳に追加
A large amount of ironware from the end of the Yayoi period were excavated from sites along the coastal areas of the Genkai-nada Sea, but very little were excavated from sites along the coastal areas of the Seto Inland Sea and Kinki region. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
弥生時代における鉄器の生産には、材料となる鉄を切り・折り取り、刃を磨き出すことによって作られる鏨切り技法と、鍛造により形を作り出す鍛造技法があることがわかっている(ごく一部の例について、鋳造により作られた可能性が示唆されているが、鉄を溶かすためにはきわめて高温の操業に耐えうる炉が必要であり、弥生時代にこのような技術が存在したかどうかは疑問視されている)。例文帳に追加
There are two types of ironware manufacturing methods during the Yayoi period; a cold chisel cutting method that cuts/breaks off iron material and grind to sharpen its edge, and a forging method that create shapes by forging (Although a very few cases are suspected with a possibility of the casting method, a furnace that can withstand operation at high temperature is required to melt iron and it is questionable if there was such technology during the Yayoi period.) - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
| 意味 | 例文 (14件) |
| 本サービスで使用している「Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス」はWikipediaの日本語文を独立行政法人情報通信研究機構が英訳したものを、Creative Comons Attribution-Share-Alike License 3.0による利用許諾のもと使用しております。詳細はhttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ および http://alaginrc.nict.go.jp/WikiCorpus/ をご覧下さい。 |
| 日本語ワードネット1.1版 (C) 情報通信研究機構, 2009-2024 License. All rights reserved. WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University. All rights reserved.License |
| Copyright © National Institute of Information and Communications Technology. All Rights Reserved. |
| Copyright (c) 1995-2024 Kenkyusha Co., Ltd. All rights reserved. |
| Copyright (C) 1994- Nichigai Associates, Inc., All rights reserved. 「斎藤和英大辞典」斎藤秀三郎著、日外アソシエーツ辞書編集部編 |
|
ログイン |
Weblio会員(無料)になると
|
|
ログイン |
Weblio会員(無料)になると
|