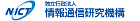| 例文 (49件) |
"建永"を含む例文一覧と使い方
該当件数 : 49件
鎌倉時代、建永2年(1207年)頃の作。例文帳に追加
It was constructed around 1207 in the Kamakura Period. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
建永3年(1209年)に僧正に就任した。例文帳に追加
In 1209, he assumed the post of Sojo (high‐ranking Buddhist priest). - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
建永元年(1206年)に出家し引退(戒名は寂恵)。例文帳に追加
In 1206 he retired and became a priest (his Buddhist name, Jakue). - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
建永元年(1206年)、鎌倉幕府政所別当辞職。例文帳に追加
In 1206, he resigned from Director of the Administrative Board of the Kamakura bakufu. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
建永2年(1207年)1月13日(旧暦)に叙従三位。例文帳に追加
On February 18, 1207, he was appointed as Jusanmi (Junior Third Rank). - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
建永2年(1207年)に右大臣(1207年-1208年)となる。例文帳に追加
He was appointed to Udaijin in 1207, and served until 1208. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
その三年後の建永元年、重源はこの世を去った。例文帳に追加
Three years later, in 1207, Chogen passed away. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
そのことが承元の法難(建永の法難)を招く原因ともなった。例文帳に追加
This practice became the reason for the religious persecution called Jogen no Honan (Kenei no Honan). - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
建永2年(1207年)3月、四国に流罪の時も当御房から出発した。例文帳に追加
In April 1207, it was from this chamber that he set out for Shikoku after being exiled from Kyoto. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
栄西自筆唐墨筆献上状建永二年六月廿一日例文帳に追加
Certificate of the present of Chinese calligraphy ink brushes written by Eisai: dated July 24, 1207 - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
1207年(建永2)1月5日、従一位に昇叙し、関白左大臣如元。例文帳に追加
February 10, 1207: Promoted to Juichii (Junior First Rank), retained his positions as Kanpaku and Sadaijin. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
建永元年(1206年)重源の後を受けて東大寺勧進職に就任。例文帳に追加
He was appointed to Daikanjin at Todai-ji Temple ceded by Chogen in 1206. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
1206年(建永元年)栄西のあとを受けて東大寺勧進となった。例文帳に追加
In 1206, he succeeded Eisai as a Kanjin (the priest who collects contributions) of Todai-ji Temple. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
没年については1204年〈元久元年)とされるが、1206年〈建永元年〉ごろまで生きていたようである。例文帳に追加
Although the year of his death was said to be 1204, it seems that he lived up to around 1206. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
そして建永元年(1206年)、遵西とともに流罪に処せられ、法然より破門された。例文帳に追加
Eventually in 1206 he was expelled together with Junsai and was excommunicated by Honen. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
建永元年(1206年)には東大寺別当、翌承元元年(1207年)7月には東寺長者。例文帳に追加
In 1206, he became a Betto (the head priest) of Todai-ji Temple, and he became a To-ji choja (the chief abbot of To-ji Temple) in August in the following year, 1207. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
1207年(建永2)1月5日、正二位に昇叙し、権中納言・左近衛大将・橘氏長者如元。例文帳に追加
February 10, 1207: He was promoted to Shonii (Senior Second Rank) and retained his position as Gon chunagon, Sakonoe no daisho, and Tachibanashi choja. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
建永元年(1206年)、九条良経の死去により、氏長者と摂政に就任。例文帳に追加
When Yoshitsune KUJO died in 1206, he became the head of his clan and was appointed Sessho (regent). - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
元久元年(1204年)に権大納言、さらに建永元年(1206年)大納言となった。例文帳に追加
He became Gon Dainagon (provisional chief councilor of state) in 1204 and Dainagon (a chief councilor of state) in 1206. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
建永元年(1206年)に叔父の将軍源実朝(源實朝)の猶子となった。例文帳に追加
In 1206, he was adopted by his uncle, Shogun MINAMOTO no Sanetomo (MINAMOTO no Sanetomo). - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
重源(ちょうげん1121年(保安(元号)2年)-1206年7月12日(建永元年6月5日(旧暦)))は、平安時代末期から鎌倉時代にかけての僧。例文帳に追加
Chogen (1121 - 19 July, 1206) was a Buddhist monk from the end of the Heian period to the Kamakura period. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
1206年(建永元年)後鳥羽上皇から山城国栂尾(とがのお)を下賜されて高山寺を開山し、観行と学問にはげんだ。例文帳に追加
In 1206, he founded Kozan-ji Temple when Toganoo of Yamashiro Province was given to him by the retired Emperor Gotoba and strove for kangyo (practice of observation and contemplation) and study. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
1206年(建永元年)仁和寺の道法法親王を師として出家・受戒し、1212年(建暦2年)に伝法灌頂を受けた。例文帳に追加
In 1206, he became a priest and received religious precepts under the priestly Imperial Prince Doho of Ninna-ji Temple and in 1212, he received denpo-kanjo (consecration for the Transmission of the Dharma). - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
蓮生墓所 建永2年9月4日(1207年9月27日)熊谷で予告往生を遂げた蓮生の遺骨は遺言により、念仏三昧院に安置された。例文帳に追加
Rensho graveyard: Rensho's body in Kumagaya. which was predictive of his birth in the Pure Land on September 27, 1207, was enshrined at Nenbutsu Zanmai-do Temple according to his will. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
また、建永元年(1206年)の興福寺が院に訴えた中にも、幸西の名が挙げられているなど、法然門下として活発な活動をした。例文帳に追加
Also, in 1206, when Kofuku-ji Temple appealed to In (the retired emperor), his name was pointed out, showing that he was energetically engaged in activities as a follower of Honen. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
結局、1207年(承元元年)法然が土佐に流罪となった建永の法難では阿波国に流罪となった。例文帳に追加
As a result, in 1207, when Honen was forced into exile to Tosa in the Kenei no honan (Kenei Persecution), he became exiled to Awa Province. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
遵西(じゅんさい、生年不詳-建永2年2月9日(旧暦)(1207年3月9日))は、平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての浄土宗の僧。例文帳に追加
Junsai (year of birth unknown - March 16, 1207) was a priest of the Jodo (Pure Land) sect of Buddhism who lived from the late Heian period to the early Kamakura period - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
法然は建永2年(1207年)には讃岐国(香川県)に流罪となり、4年後の建暦元年(1211年)には許されて都に戻るが、翌年の1月、80歳で没した。例文帳に追加
In 1207, Honen was exiled to Sanuki Province (modern day Kagawa Prefecture) but was pardoned 4 years later in 1211 and returned to Kyoto where he died the following January aged 80. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
「四十八巻伝」27では、蓮生は建永2年9月4日(1207年9月27日))に熊谷市の生家で往生したとされる(別説があるがこれが一般的)。例文帳に追加
According to No. 27 of 'The Forty-Eight Scrolls,' Rensho passed away on September 27, 1207 at his birthplace in Kumagaya City (although there are other theories, this is the generally accepted theory). - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
その後、鎌倉に下って建永元年(1206年)頃より、征夷大将軍となった実朝の侍読(教育係)となる。例文帳に追加
Then, he moved to Kamakura around 1206 and became Jidoku (tutor) for seii taishogun (literally, "great general who subdues the barbarians") Sanetomo. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
建永元年(1206年)2月22日、従四位へ昇り、10月20日には母の命により兄頼家の次男である公暁を猶子とする。例文帳に追加
On April 8, 1206, he was promoted to the rank of Jushii (Junior Fourth Rank), and on November 28, he adopted Kugyo, the second son of his brother Yoriie, at his mother's command. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
二階堂行方(にかいどうゆきかた、建永元年(1206年)-文永4年(1267年))は鎌倉時代中期の幕府実務官僚。例文帳に追加
Yukikata NIKAIDO (1206 - 1267) was a governmental official responsible for practical works in the mid Kamakura period. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
建永元年(1206年)に権大納言、建保3年(1215年)に大納言に任命され、建保6年(1218年)に大納言を辞任する。例文帳に追加
In 1206, he was appointed as Gon Dainagon (Provisional Chief Councilor of State), and in 1215, he was appointed as Dainagon (Chief Councilor of State), but in 1218, he resigned his position as Dainagon. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
1207年(建永2年・承元元年)、鎌倉幕府が興福寺の強訴に従い、法然は譛岐国に流罪となった。例文帳に追加
In 1207, the Kamakura bakufu bowed to the demands from Kofuku-ji Temple and Honen was exiled to Sanuki Province. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
また11月には銀目取引の通用銀建(永字銀、三ツ宝銀、四ツ宝銀)が新銀建(正徳銀)と変更された。例文帳に追加
In November, silver coin (eiji-gin, mitsuho-gi, and yotsuho-gin) for trading by silver was changed to new silver (shotoku-gin). - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
1206年(建永元年)、景平は、長男小早川茂平に沼田本荘を与え、次男小早川季平には沼田新庄を与えた。例文帳に追加
In 1206, Kagehira gave the Nuta Honjo to his eldest son Shigehira KOBAYAKAWA and Nuta Shinjo to his second son Suehira KOBAYAKAWA. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
建永2年(1207年)2月、興福寺の訴えにより、専修念仏の停止と、遵西など4名を死罪、法然・親鸞ら8名が流罪となった(承元の法難)。例文帳に追加
In February, 1207, at the protest of Kofuku-ji Temple, Honen's "Exclusive Nenbutsu" was suppressed, and 4 people including Junsai were executed, and 8 people including Honen and Shinran were to be banished (this incident is called Jogen no Honan). - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
(天理大学附属天理図書館蔵)古文尚書巻第十一、世俗諺文上巻、類聚三代格巻第三、作文大躰、古文孝経、蒙求 康永四年書写、蒙求 建永元年及建保六年奥書、文選巻第廿六例文帳に追加
(Tenri University Tenri Library collection) Kobunshosho scroll no. 11, Sezoku Genbun vol. 1, Ruijisandaikyaku no. 3, Sakubun Daitai, Kobun Kokyo, Mougyu (copy from Kouei Year 4), Mougyu (prefaces from Kenei Year 1 and Kenpo Year 6), Monzen no. 26 - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
明恵は建永元年(1206年)、34歳の時に後鳥羽天皇から栂尾の地を与えられ、また寺名のもとになった「日出先照高山之寺」の額を下賜された。例文帳に追加
In the year 1206 aged 34, Myoe was granted land at Toganoo by Emperor Gotoba who also conferred upon the temple the name 'Hi-idete-mazu-terasu-Kozan-no-tera' (First Mountain Temple Illuminated by the Rising Sun). - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
建永元年の中興から20数年を経た寛喜2年(1230年)に作成された高山寺境内の絵図(重文、神護寺蔵)が現存しており、当時の様子が具体的にわかる点で貴重である。例文帳に追加
A surviving diagram of the Kozan-ji Temple precinct (Important Cultural Property, housed at Jingo-ji Temple) was created in 1230, over 20 years after its 1206 revival, and has been extremely valuable in verifying the layout of the temple at the time. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
熊谷直実(くまがいじろうなおざね、永治元年2月15日(1141年3月24日)-建永2年9月4日(1207年9月27日))は平安時代末期から鎌倉時代初期の平家の武将。例文帳に追加
Naozane KUMAGAI (March 31, 1141- October 4, 1207) was busho (Japanese military commander) of the Taira family who lived during the end of Heian period until the early Kamakura period. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
しかし興福寺の奏状により念仏停止の断が下され、のち建永2年(承元元年・1207年)法然は還俗され藤井元彦を名前として、土佐国(実際には讃岐国)に流罪となった。例文帳に追加
However, a letter from Kofuku-ji Temple ordered an end to Nenbutsu, and later, in 1207, Honen was returned to secular life and exiled in Tosa province (Sanuki province in actuality), where he took the name Motohiko FUJII. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
建久9年(1198年)土御門天皇践祚の大嘗祭検校をつとめ、元久2年(1205年)には内大臣に任じられるも、翌建永元年(1206年)3月13日に辞職、11月27日に出家した。例文帳に追加
Though he served as Daijosai Kengyo in accession (to the throne) of the Emperor Tsuchimikado in 1198 and was appointed to Naidaijin in 1205, he resigned on April 29, 1206 and entered the priesthood on January 4, 1207. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
栄西は後鳥羽天皇の信頼を得た、力を持った僧であったが、この栄西が大勧進に就いた(在任、建永元年(1206年)-建保3年(1215年))ことが、東大寺に苦境をもたらした。例文帳に追加
Although Eisai was a powerful monk, on whom Emperor Gotoba relied, Eisai's assumption of the post as great fund raiser (in office from 1206 to 1215) brought hardship to Todai-ji Temple. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
蓮生は建永元年8月(1206年)翌2月8日に極楽浄土に生まれると、予告往生の高札を武蔵村岡の市に立てたが果たせず、京都に戻り、ここ東山の草庵で、承元2年9月14日(1208年10月25日)に往生したと「吾妻鏡」にある(別説あり)。例文帳に追加
According to 'Azuma Kagami' (The Mirror of the East), in September of 1206, Rensho set a notice board in a town in Musashimuraoka predicting his death in the near future and rebirth in Gokuraku Jodo (the Amida Pure Land), but the prediction failed; he returned to Kyoto and passed away on October 25, 1208 in this thatched hut of Mt. Higashi (although there are other theories as well). - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
実朝の重胤の寵愛振りを示す出来事として『吾妻鏡』では建永元年(1206年)11月に、重胤が下総国の東荘(現在の千葉県東庄町)に帰ってしまい、なかなか帰ってこないので重胤に和歌を送って帰国を促した。例文帳に追加
An incident showing Sanetomo's favor of Shigetane was written in "Azuma Kagami" (the Mirror of the East) that in November, 1206, Sanetomo sent a waka (a traditional Japanese poem of thirty-one syllables) to Shigetane to urge him to return to Kamakura, because he had gone to To estate in Shimousa Province (currently Tonosho-machi Town in Chiba Prefecture) and stayed there for a long time. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
| 例文 (49件) |
| 本サービスで使用している「Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス」はWikipediaの日本語文を独立行政法人情報通信研究機構が英訳したものを、Creative Comons Attribution-Share-Alike License 3.0による利用許諾のもと使用しております。詳細はhttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ および http://alaginrc.nict.go.jp/WikiCorpus/ をご覧下さい。 |
| Copyright © National Institute of Information and Communications Technology. All Rights Reserved. |
|
ログイン |
Weblio会員(無料)になると
|
|
ログイン |
Weblio会員(無料)になると
|