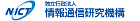| 例文 (51件) |
和哲の部分一致の例文一覧と使い方
該当件数 : 51件
和辻哲郎例文帳に追加
Tetsuro WATSUJI - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
予定調和という,哲学上の考え方例文帳に追加
a philosophical idea, called "Prastabilierte Harmonie" - EDR日英対訳辞書
1935年(昭和10年):『宗教哲学』出版。例文帳に追加
1935: He published "Philosophy of Religion." - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
1940年(昭和15年):『宗教哲学序論』出版。例文帳に追加
1940: He published "Introductory Lectures on the Philosophy of Religion." - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
白鳥庫吉、和辻哲郎らに始まる。例文帳に追加
This theory was advocated by Kurakichi SHIRATORI and Tetsuro WATSUJI. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
『正法眼蔵随聞記』(和辻哲郎校訂.岩波文庫,1982年改版)例文帳に追加
"Shobogenzo Zuimonki" Edited by Tetsuro WATSUJI. Iwanami Bunko, 1982 revised edition. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
和辻倫理学(わつじりんりがく)は、和辻哲郎の展開した倫理学の体系を指す呼称。例文帳に追加
Watsuji Rinrigaku is the name of the ethical theory developed by Tetsuro WATSUJI. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
谷崎潤一郎、和辻哲郎、芦田均、木村荘太、後藤末雄、大貫晶川らが参加。例文帳に追加
The participants included: Junichiro TANIZAKI, Tetsuro WATSUJI, Hitoshi ASHIDA, Sota KIMURA, Sueo GOTO and Shosen ONUKI. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
塩津哲生(しおつあきお、1945年(昭和20年)1月22日-)は、能シテ方喜多流の能楽師。例文帳に追加
Akio SHIOTSU (January 22, 1945 -) is a shite-kata (a main actor) of the Kita school of Noh. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
小和田哲男「斎藤氏」項『戦国大名370家出自事典』新人物往来社、1996例文帳に追加
The article of 'Saito Clan' written by Tetsuo OWADA and published in "Family Histories of the 370 Famous Sengoku Daimyo" Shin-Jinbutsuoraisha Co. Ltd., 1996. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
小和田哲男「斎藤氏」項(『戦国大名370家出自事典』新人物往来社、1996。例文帳に追加
'SAITO clan' written by Tetsuo OWADA (published in "Family Histories of the 370 Famous Sengoku Daimyo", Shin-Jinbutsuoraisha Co. Ltd., 1996 - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
1950年(昭和25年)、渡米しハーバード大学やコロンビア大学等に留学し、宗教哲学を専攻する。例文帳に追加
He went to the United States in 1950 and studied religious philosophy at Harvard and Columbia University. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
現在、姫路市の主催で、和辻哲郎文化賞が毎年優れた著作に与えられている。例文帳に追加
Nowadays, Himeji City awards The Watsuji Tetsuro Bunka Sho (The Watsuji Prize for Culture) to excellent works every year. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
この事件以後、棋譜の出版が緩和され、2年後に哲斎は『四家評定・名世碁鑑』を出版した。例文帳に追加
After this incidence, publication of Kifu was simplified and 2 years later, Tessai published "Shike Hyojo: Meisei Gokagami." - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
和辻哲郎の『古寺巡礼』(1919年刊)にも当時の奈良帝室博物館が登場する。例文帳に追加
The Imperial Household Museum of Nara those days also appears in "Koji Junrei" (A Pilgrimage to Ancient Temples) written by Tetsuro WATSUJI (published in 1919). - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
日本思想史の研究を基盤に構築された和辻の倫理学の体系は、西田幾多郎の西田哲学と並び、日本人による独自の哲学体系であると言われる。例文帳に追加
The theory of ethics established by Watsuji was based on the study of the history of Japanese thought, and is a body of philosophy unique to the Japanese, together with Kitaro NISHIDA's Nishida philosophy. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
和辻哲郎(わつじてつろう、1889年3月1日-1960年12月26日)は、『古寺巡礼』『風土』などの著作で知られる日本の哲学者、倫理学者、文化史家、日本思想史家。例文帳に追加
Tetsuro WATSUJI (March 1, 1889 - December 26, 1960) was a Japanese philosopher, ethicist, cultural historian, and scholar of Japanese history of ideas who was well known for his literary works such as "Koji Junrei" (A Pilgrimage to Ancient Temples) and "Fudo" (Climate and Culture). - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
「串呂哲学」という名称は、三浦芳聖が1956年(昭和31年)に著述した『串呂哲学第一輯-絶対真理の解明』の原稿を読んだ京都の両洋学園長・中根正親(中根式速記法の創案者)が名付けたと言われている。例文帳に追加
The name 'Kanro Philosophy' is said to have been coined by Masachika NAKANE (developer of Nakane Method of Stenography), President of Ryoyo Gakuen School, who read the manuscript of "Kanro Tetsugaku Part 1 - Clarification of Absolute Truth" written by Yoshimasa MIURA in 1956. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
和辻哲郎は奈良帝室博物館に寄託されていた本像を見た感想を『古寺巡礼』(1919年)で述べている。例文帳に追加
Tetsuro WATSUJI made remarks in "Koji Junrei" (1919) about this statue, which was deposited at the Imperial Household Museum of Nara. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
和辻哲郎は、「大部分の作者である紫式部と誰かの加筆」といった形ではなく、「一つの流派を想定するべきではないか」としている。例文帳に追加
Tetsuro WATSUJI claims that it isn't a matter that 'the tale was mostly written by Murasaki Shikibu and added by somebody else,' but 'we should assume it was written by one group.' - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
くるり、ジェイソン・フォークナー、リアダン、タラフ・ドゥ・ハイドゥークス、大工哲弘、小田和正、ふちがみとふなと、Cocco例文帳に追加
Quruli, Jason Falkner, Liadan, Taraf de Haidouks, Tetsuhiro DAIKU, Kazumasa ODA, Fuchigami to Funato, and Cocco. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
くるり、TheRealGroup、reiharakami、大工哲弘&カーペンターズ、アシャ、小田和正、細野晴臣&ワールドシャイネス、ハンバートハンバート、Lana&Flip例文帳に追加
Quruli, The Real Group, rei harakami, Tetsuhiro DAIKU and the Carpenters, Asa, Kazumasa ODA, Haruomi HOSONO and the World Shyness, Humbert Humbert, and Lana and Flip. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
和辻哲郎も『古寺巡礼』(大正8年・1919年刊)でこの像を天平彫刻の最高傑作とほめたたえている。例文帳に追加
Tetsuro WATSUJI also praised this statue in "Koji Junrei (Pilgrimages to Ancient Temples)" (published in 1919) as the best work of the Tempyo sculptures (sculptures made around the Tempyo era). - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
1980年前後に奥野高広、今谷明、小和田哲男が史料調査の結果として「伊勢新九郎盛時」を後の北条早雲とする論文を発表した。例文帳に追加
Some time around 1980, Takahiro OKUNO, Akira IMATANI and Tetsuo OWADA, after examining historical archives, published a paper stating that Shinkuro Moritoki ISE later became Soun HOJO. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
橋本峰雄(はしもとみねお、1924年(大正13年)-1984年(昭和59年))は、日本の哲学者であり、法然院の第30代貫主でもあった。例文帳に追加
Mineo HASHIMOTO (1924 - 1984) was a Japanese philosopher and the thirtieth chief abbot of the Honen-in Temple. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
久世家は関宿のほかにも和泉国にも領地があり、由哲はそこの代官を務めたことがあり、長男・鈴木貫太郎はその時生まれている。例文帳に追加
The Kuze family also owned land in Izumi Province other than Sekiyado, where Yutetsu stationed as a daikan (local governor), during which his first son, Kantaro SUZUKI was born. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
三宅雪嶺(みやけせつれい、万延元年5月19日(旧暦)(1860年7月7日)-昭和20年(1945年)11月26日)は、哲学者、評論家。例文帳に追加
Setsurei MIYAKE (July7, 1860 - November 26, 1945) was a philosopher and essayist. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
小和田哲男は堀と同様の解釈をとりながら、5月4日以降に将軍任官を考えたのではないかとの見解を示している。例文帳に追加
Tetsuo OWADA with the same interpretation as Hori's presented that Nobunaga probably thought of accepting the title of the Shogun after May 4 (old calendar). - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
和辻哲郎の「巨椋池の蓮」という手記は、大正末年か昭和初年の夏に巨椋池で蓮見船に乗った思い出をつづったもので、当時の観蓮の情景を描いており、1950年(昭和25年)に発表された。例文帳に追加
A collection of notes entitled Oguraike-no-Hasu (Lotus in Ogura-ike Pond) written by Tetsuro WATSUJI, reminiscing the occasion when he was on board a lotus-viewing boat on Ogura-ike Pond in the summer of 1926 or 1927, described scenes of lotus-viewing at the time and was published in 1950. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
日本における木造仏像彫刻の古例として貴重であるとともに、大正時代以降、和辻哲郎の『古寺巡礼』、亀井勝一郎の『大和古寺風物誌』などの書物で紹介され著名になった。例文帳に追加
It is valued as an old example of wooden Buddhist sculptures in Japan; after the Taisho period, it was introduced in writings such as "Koji Junrei" (A pilgrimage to ancient temples) by Tetsuro WATSUJI and "Yamato Koji Fubutsushi" (Pilgrimage to the ancient temples of Yamato) by Katsuichiro KAMEI and became well-known. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
和辻哲郎の『古寺巡礼』は大正8年(1919年)に刊行されたものだが、『法隆寺大鏡』の記述に影響されてか、この像を「百済観音」と呼んでいる。例文帳に追加
The "Koji Junrei" by Tetsuro WATSUJI, which was published in 1919, calls this statue 'Kudara Kannon', maybe as influenced by the description of "Horyu-ji Okagami". - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
和辻哲郎は、「帚木」巻の冒頭部の記述についての分析などから、「とにかく現存の源氏物語が桐壺より初めて現在の順序のままに序を追うて書かれたものではないことだけは明らかだと思う。」と結論付けた。例文帳に追加
Tetsuro WATSUJI concluded, 'Anyway, it is totally clear that 'The Tale of Genji' was not written in the order of the present text beginning with Kiritsubo,' depending on the analysis of the opening lines in the chapter of 'Hahakigi.' - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
たとえば昭和28年(1953年)国税庁の鑑定官であった田中哲朗を中心として、全国の有志酒蔵が、当時の時流であった三増酒に抗して品質の高い酒を造ろうと研醸会を結成している。例文帳に追加
For example, led by Tetsuro TANAKA who was an Official Appraiser of the National Tax Administration Agency, some voluntary sake breweries from all over Japan organized Kenjokai (the study group of sake brewing) in 1953 in order to produce high quality sake as opposed to sanzoshu which was popular at that time. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
大正・昭和期の名人として喜多実、後藤得三ついで友枝喜久夫・友枝昭世親子、粟谷菊生、塩津哲生らが知られている。例文帳に追加
Minoru KITA, Tokuzo GOTO were great actors of this school of the Taisho and the Showa periods, and after them, other masters such as Kikuo TOMOEDA, Akiyo TOMOEDA (Kikuo and Akiyo are father and son), Kikuo AWAYA, and Akio SHIOTSU appeared from this school. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
それをもとに関西医科大学の石田哲郎の指導のもと、昭和55年(1980年)3月、日本画家前田幹雄の手によって石膏の復顔肖像画が制作された。例文帳に追加
In March, 1980, the Japanese-style painter Mikio MAEDA drew a portrait of Mitsunari from the plaster-reconstructed face under the direction of Tetsuro ISHIDA, of Kansai Medical University. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
西田幾多郎(にしだきたろう、1870年5月19日(明治3年4月19日(旧暦))-1945年(昭和20年)6月7日)は日本を代表する哲学者であり京都大学教授、名誉教授。例文帳に追加
Kitaro NISHIDA (May 19, 1870 - June 7, 1945) was a representative Japanese philosopher, professor and honorary professor of Kyoto University. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
1960年(昭和35年)、日米安全保障条約の改定に際して、同じ首相経験者の石橋湛山、片山哲とともに岸信介首相(当時)に退陣を勧告している。例文帳に追加
In 1960, at the time of revision of the Japan-US Security Treaty, he, along with Tanzan ISHIBASHI and Tetsu KATAYAMA, also a former Prime Minister, urged Nobusuke KISHI, the current Prime Minister, to resign. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
江戸時代後期の蘭学者・高野長英は後藤の大叔父に当たり、甥に政治家の椎名悦三郎、娘婿に政治家の鶴見祐輔、孫に社会学者の鶴見和子、哲学者の鶴見俊輔、演出家の佐野碩をもつ。例文帳に追加
Choei TAKANO, a scholar of the Western studies (rangakusha) of the late Edo Period, was his granduncle, a politician Etsusaburo SIINA, his nephew, the politician Yusuke TSURUMI, a son-in-law who married with his daughter, and a sociologist Kazuko TSURUMI, a philosopher Shunsuke TSURUMI, a theatrical director Seki SANO are his grandchildren. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
天保9年(1838年)に安井家の跡目安井算知(俊哲)を七段昇段を認めたことで、元美は井上幻庵因碩を添願人として、丈和との二十番の争碁願いを提出する。例文帳に追加
In 1838, Genbi submitted a request for Sogo (official challenge match) of Nijuban against Jowa, with Gennaninseki INOUE as tengannin, since Sanchi (Shuntetsu) YASUI, the heir of Yasui family, was approved to be promoted to seventh-dan. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
第二次世界大戦後の1947年(昭和22年)、片山哲内閣により、日本国憲法にふさわしい祝日の法案に紀元節が「建国の日」として盛り込まれていたが、連合国軍最高司令官総司令部により削除され、法は1948年(昭和23年)7月に施行された。例文帳に追加
After World War II in 1947 the cabinet of Tetsu KATAYAMA proposed a bill on public holidays appropriate to the constitution of Japan including Empire Day as "Foundation Day" (kenkoku no hi), but this was dismissed by the General Headquarters of the Supreme Commander for the Allied Powers and the law came into effect in July 1948. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
この四人は1942年(昭和17年)から翌年にかけて『中央公論』誌上で三回にわたり掲載された「世界史的立場と日本」座談会(「世界史的立場と日本」昭和十七年一月号、「東亜共栄圏の倫理性と歴史性」昭和十七年四月号、「総力戦の哲学」昭和十八年一月号)の出席者である。例文帳に追加
These four people were participants in the symposium entitled 'World-historical position and Japan' printed in the three issues of "Chuo Koron" from 1942 to the following year (January 1942 issue 'World-historical position and Japan,' April 1942 issue 'Morality and historical aspect of the East Asia Co-prosperity Sphere' and January 1943 issue 'Philosophy of all-out war'). - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
第二次世界大戦のさなか、1942年から翌年にかけて『中央公論』誌上で、「世界史的立場と日本」座談会(「世界史的立場と日本」昭和17年1月号、「東亜共栄圏の倫理性と歴史性」昭和17年4月号、「総力戦の哲学」昭和18年1月号)を京都大学の同僚、高坂正顕、西谷啓治、鈴木成高と行った。例文帳に追加
From 1942 to 1943 during World War II, articles summarizing symposiums that Iwao KOYAMA held with Masaaki KOSAKA, Keiji NISHITANI, and Shigetaka SUZUKI (colleagues of his from Kyoto Imperial University) on topics such as ' The world's historical position and Japan' appeared in the magazine "Chuo Koron" ('The world's historical position and Japan' appeared in the January issue in 1942, 'The morality and history of the Great East Asia Co-prosperity Sphere' appeared in the April issue in 1942, and 'The philosophy of all-out battle' appeared in the January issue in 1943). - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
嘉吉3年(1441年)、嘉吉の乱に際して父範忠の名代として1,000騎を率いて尾張国まで出陣している(『今川記』では今川範政とされているが、小和田哲男静岡大学教授によると範政は永享5年(1433年)に没しており、名代は義忠と思われる)。例文帳に追加
In 1441, he went to Owari Province leading 1,000 horse soldiers, to fight in the Kakitsu War as a representative for his father, Noritada (it is written in the "Imagawa-ki," that Norimasa IMAGAWA went to the Kakitsu War, but Tetsuo OWADA, a professor at Shizuoka University, maintains that Norimasa died in 1433 and Yoshitada was the one who fought in the war). - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
そのため池田亀鑑などはこの伝承を「とりあげるに足りない奇怪な説」に過ぎないとして事実ではないとしているが、和辻哲郎は、「現在の源氏物語には読者が現在知られていない光源氏についての何らかの周知の物語が存在することを前提として初めて理解できる部分が存在する。」として「これはいきなり斥くべき説ではなかろうと思う」と述べている。例文帳に追加
Therefore, Kikan IKEDA considers the folklore to be an untruth, as 'a bizarre rumor that doesn't deserve to be taken seriously'; however, Tetsuro WATSUJI states, 'The Tale of Genji has mysterious parts that readers can't understand until they have noticed the existence of some other tales on Hikaru Genji, which the present readers don't know about but once existed,' adding, 'This is not a supposition that should be immediately rejected.' - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
昭和31年(1956年)には歌人の職能的性格を持つ団体として「現代歌人協会」が、生方たつゑ・扇畑忠雄・尾上紫舟・香川進・鹿児島壽蔵・木俣修・窪田空穂・近藤芳美・佐々木信綱・佐藤佐太郎・紫生田稔・土屋文明・坪野哲久・土岐善麿・松村英一・会津八一・宮柊二・山口茂吉・山本友一など62名の発起人により結成された。例文帳に追加
In 1956, Gendai Kajin Kyokai (The Association of Contemporary Tanka Poets) was formed as something similar to a professional association by 62 founding members, including Tatsue UBUKATA, Tadao OOGIHATA, 尾上紫舟, Susumu KAGAWA, Juzo KAGOSHIMA, Osamu KIMATA, Utsubo KUBOTA, Yoshimi KONDO, Nobutsuna SASAKI, Sataro SATO, 紫生田稔, Bunmei TSUCHIYA, Tetsukyu TSUBONO, Zenmaro TOKI, Eiichi MATSUMURA, Yaichi AIZU, Shuji MIYA, Mokichi YAMAGUCHI and Tomoichi YAMAMOTO. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
2005年放送の「その時歴史が動いた:戦国をひらいた男~北条早雲 56才からの挑戦~」(日本放送協会、ゲスト:小和田哲男静岡大学教授)では、早雲を幕府の高級官僚としているが、年齢については享年88説を採り「大器晩成」として描いている(諸説を検討の結果一般的な説を採用したとのこと)。例文帳に追加
In the documentary, "Movement of History: The Man that started the Warring States Period - Soun HOJO, Challenge from the age of 56" (NHK, Guest: Tetsuo OWADA, Professor of Shizuoka University), broadcast in 2005, Soun is described as 'a late bloomer' who became a high ranking officer in the Bakufu government and who died at the age of 88 (a generally accepted theory that was adopted after reviewing various theories). - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
754年(天平勝宝6年)1月に6度目の航海のすえに平城京に到着して、戒律や多数の経典を伝えた唐出身の鑑真和尚、大仏開眼供養の導師となったインド出身の菩提僊那、菩提僊那と同時に来日したチャンパ王国(林邑)出身の僧仏哲、唐僧道セン、また、多くの新羅僧ら外国出身の僧侶の活動に負うところも大きかった。例文帳に追加
It also owed to activities of foreign monks such as Ganjin (Jianzhen) wajo from Tang who arrived in January 754 in Heijokyo on his sixth attempted voyage to Japan and introduced the precepts of Buddhism, bringing a large number of Buddhist scriptures, Bodai Senna from India who acted as Kaigan doshi (an officiating priest to consecrate a newly made Buddhist statue or image by inserting the eyes) for the daibutsu, Buttetsu, a monk from the kingdom of Champa (Lin Yi, a former name for Vietnam) who came to Japan at the same time as Tang monk Bodai Senna (Dosen) and a large number of monks from Silla. - Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
| 例文 (51件) |
| 本サービスで使用している「Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス」はWikipediaの日本語文を独立行政法人情報通信研究機構が英訳したものを、Creative Comons Attribution-Share-Alike License 3.0による利用許諾のもと使用しております。詳細はhttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ および http://alaginrc.nict.go.jp/WikiCorpus/ をご覧下さい。 |
| Copyright © National Institute of Information and Communications Technology. All Rights Reserved. |
|
ログイン |
Weblio会員(無料)になると
|
|
ログイン |
Weblio会員(無料)になると
|